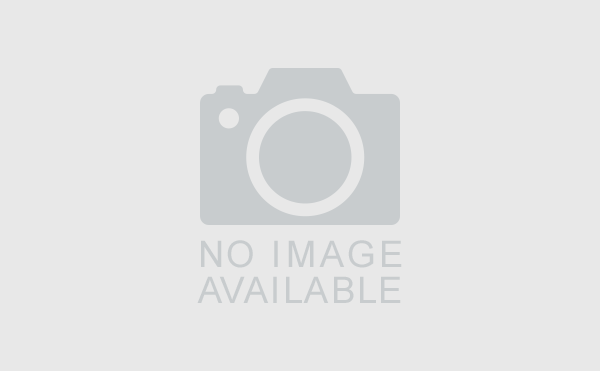安心感がチームを動かす ~心理的安全性のある職場とは~
「心理的安全性」という言葉を耳にしたことはありますか?
これは、安心して意見を言えたり、失敗をしても非難されず学びに変えられたりする状態を指します。安心感があるからこそ、人は自分の気持ちや考えを出すことができ、チームの中で協力し合いやすくなります。
実際に、Googleが180以上のチームを対象に行った「プロジェクト・アリストテレス」という研究でも、心理的安全性の高い組織ほど生産性、学習意欲、創造性が高いことが示されています。
つまり、心理的安全性は個人にとっても組織にとっても成長の土台になるのです。
では、どうすれば心理的安全性のある職場をつくることができるのでしょうか。いくつか大事なポイントがあります。
・失敗や意見を否定しないこと
間違いや弱音を責めるのではなく、「学び」に変えようとする姿勢があると、人は安心して挑戦できます。
・気持ちを共有し合えること
自分の感情を話しても受けとめてもらえる、聴いてもらえる、という体験があると「ここでなら大丈夫」と思えるようになります。
・違いを尊重すること
立場や考え方が違っても、「それも大切な視点だね」と認め合う。多様性があるからこそ、チームはしなやかに力を発揮できます。
・リーダーが率先して示すこと
上の立場の人が自分の弱さや課題もオープンにする。それが職場全体の安心感につながっていきます。
先日、ある病院で研修を担当した際に、このことを実感しました。
研修の冒頭には、院長・副院長・事務長と事務職の方々が登場して、患者対応の難しい場面を演じてくださったのです。
立場の高い方々が楽しそうに役を引き受け、会場に笑いが起こり、自然に和やかな雰囲気が広がっていきました。
これは「リーダーのふるまいが安心感をつくる」ことの大きな例だと思います。
また、グループごとのワークでも会話がとても盛り上がりました。終了の合図をしても、まだ話し足りないといった様子のグループもありました。
参加者の感想には、
「感情を共有することでチーム力をより高めたい」
「自分の感情も労ってあげたい」
「相手の感情にもしっかり目を向けたい」
「“ちくしょー”と思ってしまう気持ちも大切にしていいと知った」
といった声があり、一人ひとりが自分の体験として気づきを持ち帰ってくださったことが伝わってきました。
もちろん、日常業務に追われて「気持ちを共有する時間なんてない」という瞬間もあると思います。
けれど、その小さな共有や「大丈夫だよ」という雰囲気の積み重ねこそが、心理的安全性を育てる土台になります。
安心して声を出せる場があると、人は力を発揮できます。そして、その積み重ねが組織の力を高めていきます。
心理的安全性のある職場は、一人ひとりの気持ちを大切にしながら、しなやかに成長していける職場だと思います。
私自身、研修講師として関わるときに大切にしていることがあります。
一方的に知識を伝える講義形式ではなく、できるだけフロアの声を拾いながら進めること。
参加者が自分の気持ちや経験を言葉にできるような仕掛けをつくること。
こうした工夫を意識しながら、今後も研修講師のお仕事をいただいた際には、研修そのものが心理的安全性の高い場になるよう、私もさらに工夫を重ねていきたいと思っています。
さて、あなたの職場には、心理的安全性を感じられる瞬間はありますか?
もしあまり感じられないとしたら、まずは身近な仲間と仕事にまつわるモヤモヤを共有してみてください。
もしあなたがリーダーの立場にあるなら、思い切って自分の弱みを見せてみてください。
そんな小さなアプローチの積み重ねで、職場の雰囲気は少しずつ変わっていくはずです。
自分の関わりがそのきっかけになると思えたら、素晴らしい役割を担っていることへの誇りや、組織が変わっていくかもしれない期待で、ひそかにワクワクできるのではないでしょうか。
これは、安心して意見を言えたり、失敗をしても非難されず学びに変えられたりする状態を指します。安心感があるからこそ、人は自分の気持ちや考えを出すことができ、チームの中で協力し合いやすくなります。
実際に、Googleが180以上のチームを対象に行った「プロジェクト・アリストテレス」という研究でも、心理的安全性の高い組織ほど生産性、学習意欲、創造性が高いことが示されています。
つまり、心理的安全性は個人にとっても組織にとっても成長の土台になるのです。
では、どうすれば心理的安全性のある職場をつくることができるのでしょうか。いくつか大事なポイントがあります。
・失敗や意見を否定しないこと
間違いや弱音を責めるのではなく、「学び」に変えようとする姿勢があると、人は安心して挑戦できます。
・気持ちを共有し合えること
自分の感情を話しても受けとめてもらえる、聴いてもらえる、という体験があると「ここでなら大丈夫」と思えるようになります。
・違いを尊重すること
立場や考え方が違っても、「それも大切な視点だね」と認め合う。多様性があるからこそ、チームはしなやかに力を発揮できます。
・リーダーが率先して示すこと
上の立場の人が自分の弱さや課題もオープンにする。それが職場全体の安心感につながっていきます。
先日、ある病院で研修を担当した際に、このことを実感しました。
研修の冒頭には、院長・副院長・事務長と事務職の方々が登場して、患者対応の難しい場面を演じてくださったのです。
立場の高い方々が楽しそうに役を引き受け、会場に笑いが起こり、自然に和やかな雰囲気が広がっていきました。
これは「リーダーのふるまいが安心感をつくる」ことの大きな例だと思います。
また、グループごとのワークでも会話がとても盛り上がりました。終了の合図をしても、まだ話し足りないといった様子のグループもありました。
参加者の感想には、
「感情を共有することでチーム力をより高めたい」
「自分の感情も労ってあげたい」
「相手の感情にもしっかり目を向けたい」
「“ちくしょー”と思ってしまう気持ちも大切にしていいと知った」
といった声があり、一人ひとりが自分の体験として気づきを持ち帰ってくださったことが伝わってきました。
もちろん、日常業務に追われて「気持ちを共有する時間なんてない」という瞬間もあると思います。
けれど、その小さな共有や「大丈夫だよ」という雰囲気の積み重ねこそが、心理的安全性を育てる土台になります。
安心して声を出せる場があると、人は力を発揮できます。そして、その積み重ねが組織の力を高めていきます。
心理的安全性のある職場は、一人ひとりの気持ちを大切にしながら、しなやかに成長していける職場だと思います。
私自身、研修講師として関わるときに大切にしていることがあります。
一方的に知識を伝える講義形式ではなく、できるだけフロアの声を拾いながら進めること。
参加者が自分の気持ちや経験を言葉にできるような仕掛けをつくること。
こうした工夫を意識しながら、今後も研修講師のお仕事をいただいた際には、研修そのものが心理的安全性の高い場になるよう、私もさらに工夫を重ねていきたいと思っています。
さて、あなたの職場には、心理的安全性を感じられる瞬間はありますか?
もしあまり感じられないとしたら、まずは身近な仲間と仕事にまつわるモヤモヤを共有してみてください。
もしあなたがリーダーの立場にあるなら、思い切って自分の弱みを見せてみてください。
そんな小さなアプローチの積み重ねで、職場の雰囲気は少しずつ変わっていくはずです。
自分の関わりがそのきっかけになると思えたら、素晴らしい役割を担っていることへの誇りや、組織が変わっていくかもしれない期待で、ひそかにワクワクできるのではないでしょうか。