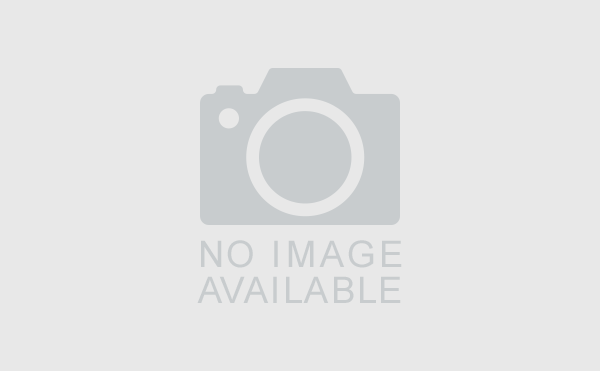結論のない話をしよう
「で、結局どうすればいいの?」「つまり、何が言いたいの?」
このように、私たちはつい“結論”を求めてしまいます。
議論をしていても、日常の会話でも、明確な答えを提示することが良しとされる場面は少なくありません。
「まず結論から話す」「要点を簡潔にまとめる」――それはもちろん、コミュニケーションの技術として大切なことですし、効率や生産性が重視される社会では、ある意味当然の姿かもしれません。
けれど私は、ときどき思うのです。
そのように“答えを急ぐ姿勢”が、実は大切なものを見落としてしまっているのではないかと。
話しているうちに、「ああでもない」「こうでもない」と言いながら、話が堂々巡りすることがあります。
何も決まらず、結論にたどり着かない。けれどその時間の中でふと、誰かの言葉に心が動かされたり、予想もしなかった気づきが生まれたりすることがあります。
自分一人ではたどり着けなかった視点に出会う瞬間。
それは、最短ルートでは決して出会えない、言葉の旅路の中でしか生まれないものだと感じています。
そして、その旅路を誰かと共有すること。それが「対話」なのだと思います。
「この人と一緒に考えている」という感覚。
その揺らぎや迷いを共有することこそが、関係性を少しずつ育てていきます。
対話とは、ただ情報をやりとりするものではなく、関係を耕す営みでもあるのです。
そんなことをふと思い出すのが、仕事を終えた夜のひとときです。
ふと気づくと、猫が私のそばにやってきて、何をするでもなく静かに横たわっています。
私はコーヒーを片手に、ぼんやりとした頭で部屋の明かりをぼーっと眺めています。
猫はまどろみながら、時折ゆっくり瞬きをしてこちらを見てきます。
言葉は交わしません。何かを決めるわけでもありません。ただ、そこに一緒にいる。
その時間が、私にはとても豊かに感じられるのです。
猫はこちらの事情などおかまいなしに、眠ったり歩いたり、外を眺めたりしています。
けれど何も起きないようでいて、その時間が確かに「意味のある時間」なのだと心の奥が知っている気がします。
私たちは「意味がある=結果が出る」「成果が見える=価値がある」と思いがちです。
けれど本当は、意味とは後からついてくるものではないでしょうか。
誰かとゆっくり話した記憶。答えが出なかった会話の断片。まとまらなかった思考の欠片。
そうしたものが、ある日ふいに自分を支えてくれたり、誰かの力になったりすることがあります。
だから私は、結論のない話をもっとしたいと思っています。
すぐに答えを出さなくても大丈夫。
むしろ、出さない時間の中にしか見えてこないものが、確かに存在するのです。
遠回りのように思えるやりとりの中に、
誰かとのつながりや、自分自身との関係性が、静かに育っている。
そのような時間を、もっと大切にしても良いのではないでしょうか。